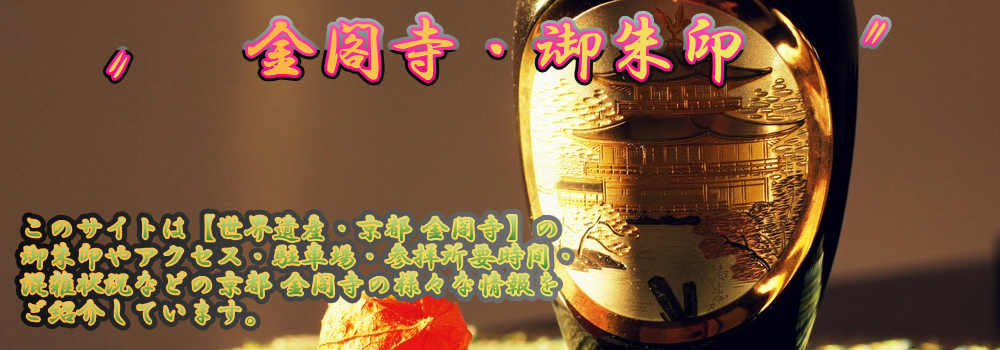京都・仁和寺「観音堂」【重要文化財】
造営年
初代、観音堂
不明(推定:928年/延長6年/平安時代)
現在(二代目観音堂)
1641年(寛永十八年)〜1644年(寛永二十一年/江戸時代初期)
再建年
2012年(平成24年)※解体修理(過去最大規模)
※2019年(令和元年)5月15日に工事終了。無事、落慶法要が営まれる。
建築様式(造り)
入母屋造り
前面一間向拝付き
大きさ
高さ(屋根):14.5メートル
四辺:約15メートル
屋根の造り
本瓦葺
重要文化財指定年月日
1973年(昭和48年)6月2日
御本尊
千手観音菩薩
法要
伝法灌頂
京都・仁和寺「観音堂」の読み方
観音堂:「かんのんどう」
「観音堂」の名前の由来
単純に内部に千手観音菩薩が奉安されることから、「観音堂」と付される。
京都・仁和寺「観音堂」の歴史
仁和寺に伝承される本寺堂院記の内容に拠ると、観音堂の創建は仁和寺創建の40年後となる928年(延長6年)頃に造営されたと伝えられています。
951年(天暦五年)3月に改造、985年(寛和元年)2月に再建、1001年(長保三年)3月炎上
、1022年(治安二年)10月復興、1119年(元永二年)4月炎上、1121年(保安二年)11月復興と興亡を繰り返す。
現在の堂は江戸初期に新造(再建)されたもの。
観音堂が創建された理由
仁和寺の寺伝によると、大師・空海が宇多天皇の第3皇子・真寂法親王の夢枕に立ち、観音堂の造営を発願されたとのことです。
その他、この観音堂は仁和寺最大の法要である「伝法灌頂(でんぼうかんじょう)」が執り行われる場所でもあり、仁和寺の諸堂の中でも重要な位置づけの堂舎となります。
伝法灌頂とは、密教における指導者としての位(阿闍梨)を授ける重要な儀式のことです。
京都・仁和寺「観音堂」の建築様式(造り)・特徴
この観音堂は江戸初期の再建時から現在に至るまで、屋根の葺き替えを一度実施したのみであり、つまりは江戸再建期の堂舎がそのまま現存していることになります。
しかし400年間雨風に耐えてきた堂舎も老朽化がみられ、2012年(平成24年)より過去最大規模となる解体修理が執り行われています。
前面がすべて板扉が据えられ、扉を開けないと内部が見えない仕様は密教寺院によく見られる様式であり、また奈良時代から平安後期にかけて見られる堂舎の特徴を示すものでもあります。
禅宗様式と和様建築が入り混じった折衷様
虹梁大瓶束
観音堂の妻側に目をやると、虹梁の上に大瓶束(たいへいづか)を載せる虹梁大瓶束(こうりょうたいへいづか)が用いられるなど、江戸時代の再建の際、以前の禅宗様を踏襲した様子が見られる。
その一方で正面の板扉は和様式を用いるなど、境内の他の堂舎が純和様式が多い中、この観音堂は孤高の存在のように見える。
三ッ花懸魚
鎌倉仏教が隆盛した鎌倉時代後期になると、中国から禅宗文化が渡来し、それらは我が国の文化に様々な影響を与えた。
例えば堂舎の建築様式というのも、そのうちの一つ。
板蟇股
板蟇股も鎌倉時代に多くの堂舎にて用いられた蟇股であり、平安期のくり抜かれた本蟇股から、板状に変形させたものになる。
板蟇股は奈良時代も数多く採り入れられたが、鎌倉期の板蟇股は平安期の背高の蟇股を変形させていることから、背高であることが大きな特徴とな〜る。
棟までの高さに注目
また、堂舎の高さにおいても時代が下るごとに高さが増していく事実を鑑みると、観音堂の堂舎は棟まで高さあることに気づきます。
したがって比較的、近代に建造された堂舎とみることができます。
観音堂の堂内の構成
内陣
北側には天井の高さが約6メートルもの二重折り上げ式の小組格天井が張られ、中央には三間の須弥壇が置かれています。正面両端に板扉、中央三間に桟唐戸を据え、天井付近には欄間がある。
須弥壇は禅宗様式が入り混じった和様式。須弥壇下、格狭間には花柄の透かし彫りが用いられる。
外陣
また南側は外陣となり、畳の間となっています。天井は組入天井を張る。
なお、内陣の板扉を閉めると内外陣の区画は完全なものとなり、これは密教的儀式を厳かに執行するための密教寺院特有の空間構成とな〜る。
観音堂の堂内にて安置される仏像群一覧
観音堂の本尊「千手観音菩薩」
仁和寺・観音堂の御本尊は「千手観音菩薩(せんじゅかんのん)」です。別名で「千手千眼観自在菩薩(せんじゅせんげん かんじざいぼさつ)」とも呼称します。
内陣須弥壇上に千手千眼観自在菩薩を中心に納置し、その両脇には脇侍として「不動明王」と「降三世明王」、「二十八部衆」が配される。
あまり知られていませんが、千手観音の手の平にはすべての衆生を漏れなく救うため、それぞれ眼があり、合計で1000個もの眼があることから千手”千眼”観自在菩薩の名前が付されています。
二十八部衆
二十八部衆は、千手観音に仕える眷属(けんぞく)になります。
降三世明王
降三世明王は、「ごうざんぜみょうおう」と読み、密教特有の仏様です。不動明王(大日如来)を守護する五大明王の一尊でもあります。
欲界・色界・無色界の三界にある三毒(貪/とん・瞋/じん・癡/ち)を降伏(ごうふく/力でねじ伏せる)する強い力を持った仏様です。
五大明王とは?
東:降三世明王(ごうざんぜみょうおう)
西:大威徳明王(だいいとくみょうおう)
南:軍荼利明王(ぐんだりみょうおう)
北:金剛夜叉明王(こんごうやしゃみょうおう)
不動明王
不動明王は大日如来がMAXに怒った時の姿であり、戦闘系に変化した姿です。
スーパーサイヤ人4ver.時間永続くらいの力を持っています。
強スケベったれ者を一例とした煩悩が強い者や強悪者に対しては容赦なく降魔の鉄槌をモロにド頭にくらわせます。
京都・仁和寺「観音堂」の場所(地図)
観音堂は中門くぐって左脇の桜苑(あむろなみ..間違い、御室桜!!)の奥に位置します。
西門から入って右へ徒歩1分ほど進んだ先にあります。
※注意※観音堂は通常は非公開になっています。また、2017年8月現在、観音堂は解体修理中につき外観を見ることすらできなくなっています。
スポンサードリンク -Sponsored Link-
当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。